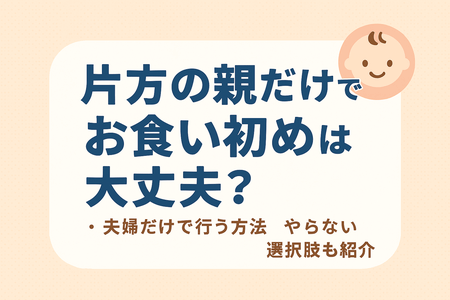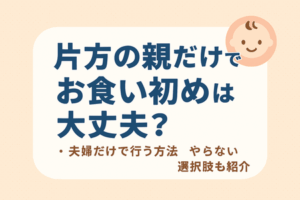
お食い初めとは?行事の基本
お食い初め(おくいぞめ)は、生後100日前後に行う伝統行事。
「これから食べ物に困らないように」という願いを込めて、赤ちゃんの口元に食べ物を近づける儀式を行います(実際に食べさせません)。
100日ちょうどにこだわる必要はなく、家族の都合に合わせて前後に調整してOK。服装も、写真に残したい方はセレモニー寄りに、落ち着いた雰囲気が好きなら普段着+ワンポイントでも十分です。
片方の親だけでお食い初めをするケースは多い
遠方・仕事・体調などの事情で、全員が同日に集まれないことはめずらしくありません。
片方の親(どちらかの祖父母)だけの参加、あるいは夫婦+子どもだけで行うご家庭もたくさんあります。
ポイントは「無理をしないこと」。
参加できなかった方には、あとで写真や動画を共有したり、短時間だけオンライン参加してもらったりすると喜ばれます。
どちらの親を呼ぶ?判断のコツと伝え方
判断のコツ
-
距離・移動負担:近居の親を優先/遠方はオンライン併用
-
健康・予定:体調や仕事を最優先
-
開催場所:自宅・外食・実家のいずれかで無理のないほう
-
今後のイベント:初節句・誕生日などで交代参加にするのも丸く収まります
角が立たない伝え方(例)
-
近居の親のみ招くとき
「今回は日程が合わず、近くの親に来てもらうことにしました。写真や動画はすぐ共有しますね。」
-
交代制の提案
「お食い初めはA家にお願いし、初節句はB家で一緒に…という形にできればと思っています。」
-
オンライン案内
「当日は○○時にビデオ通話をつなぎます。数分だけでも画面越しに一緒にお祝いできたら嬉しいです。」
夫婦だけ・家族だけで行う段取り
「夫婦だけ」「家族だけ」で行うと、赤ちゃんのペースに合わせやすくて人気です。
自宅での進行サンプル(約60〜90分)
-
準備(器・祝い膳・カメラ設置)
-
はじめのひと言(30秒でOK)
-
口元へ食べ物を近づける儀式(数回)
-
記念撮影(家族写真・手元カットなど)
-
みんなで食事/ティータイム
-
片付け・お礼の連絡
外食での進行のコツ
-
個室または半個室を選べると安心
-
赤ちゃん用のクッションやバウンサーを準備
-
予約時に「写真を撮る時間を少し取りたい」とひと言添える
誰が“口元へ運ぶ役”をする?決め方ガイド
伝統では年長者が務めることもありますが、決まりではありません。
-
親が務める:いちばん自然。写真も撮りやすい
-
祖父母が務める:長寿にあやかる意味合いで喜ばれる
-
みんなで交代:最初は祖父母→その後に父母・兄姉…と“順番に”も楽しい
「最初は祖父母、ラストは父母」という折衷案もおすすめです。
参加できない親へのフォロー|オンライン&共有の工夫
-
ビデオ通話:LINEやFaceTimeでOK。
事前に時間を決め、三脚+スピーカーがあると聞き取りやすいです。 -
写真・動画の共有:
-
シェアアルバム(Googleフォト等)にベスト10カットをまとめる
-
「家族写真/赤ちゃんアップ/儀式の手元/全体の様子/お膳」など定番ショットを押さえる
-
-
後日プチ報告(メッセージ例)
「昨日は無事にお食い初めを行いました。短い時間でしたが穏やかに過ごせました。アルバムを共有しますね。」
「やらない」「延期する」という選択肢も
体調や忙しさでどうしても難しいときは、延期・簡略化で大丈夫。
100日を過ぎても、家族が集まりやすい落ち着いた日に行えばOKです。
簡略化アイデア
-
自宅でお膳の写真だけ撮る
-
お赤飯と汁物など少数メニューで
-
カードに一言を書いて写真と一緒に送る
連絡テンプレ(招待・欠席フォロー)
-
招待(近居の親へ)
「〇月〇日、ささやかにお食い初めを行います。短時間ですがご都合が合えばご一緒いただけると嬉しいです。」
-
招待(遠方の親へ・オンライン)
「当日は○時頃にビデオ通話をつなぎます。数分だけでも画面越しにご一緒できれば心強いです。」
-
欠席フォロー
「日程の都合で今回は画面越しの参加に。写真はアルバムで共有しますね。落ち着いたら改めて集まりましょう。」
よくある疑問Q&A
Q. 片方の親だけ呼ぶのは失礼?
A. 事情があれば問題ありません。後日写真・動画の共有や、次の行事で交代参加にするなど配慮の一言があれば十分です。
Q. どちらの親を優先すべき?
A. 距離や体調、都合の合いやすさを優先しましょう。公平性は次の行事で交代するなど、長い目で調整すると安心。
Q. 服装は?
A. 写真に残したい場合はセレモニー寄り、動きやすさ重視ならきれいめカジュアルでOK。
Q. 当日の所要時間は?
A. 儀式と写真で30〜60分、食事を入れて90分前後が目安です。赤ちゃんの様子最優先で。
準備チェックリスト(自宅開催向け)
-
祝い膳(鯛、赤飯、汁物、煮物、香の物 など/無理のない範囲で)
-
器(祝い箸・小皿・お椀)/ランチョンマット
-
歯固めの石(なければ硬い飾り石の代替・専用の飾りでもOK)
-
赤ちゃんのケア用品(ガーゼ・ミルク・おむつ・着替え)
-
カメラ・スマホ三脚・タイマー/ビデオ通話用端末
-
記念の小物(カード・名札・ガーランド など)
まとめ|“うちのやり方”がいちばん
お食い初めは、家庭ごとに無理のない形で行えば大丈夫。
片方の親だけ・夫婦だけでも十分に温かい時間になりますし、参加できない家族には共有の工夫で気持ちを届けられます。
大切なのは、節目を穏やかに祝い、みんなで喜びを分かち合うこと。
形式にとらわれすぎず、“うちのやり方”で心地よいお食い初めを迎えてくださいね