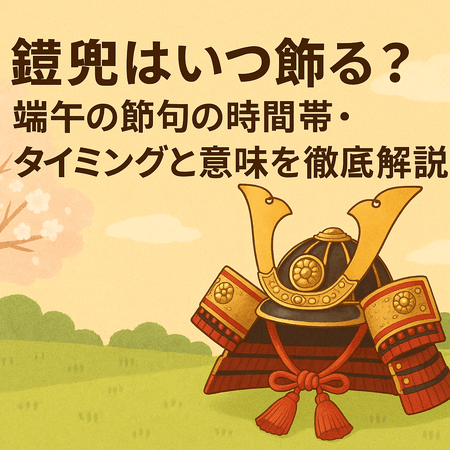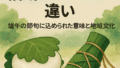鎧兜を飾るのはいつからいつまで?飾る時期の目安
鎧兜を飾る時期は、春分(3月20日頃)を過ぎたころから4月上旬までが一般的な目安です。
立春を過ぎて少し暖かさを感じるころに飾り始める家庭も多く、早めに出すことで「災いを遠ざけ、子どもの健やかな成長を長く祈る」期間を持つことができます。
「うっかり出すのを忘れてしまった」という場合でも、端午の節句(5月5日)の1週間前までに飾れば問題ありません。
行事は日付よりも「心を込めて行うこと」が大切で、少し遅れても縁起を損なうことはありません。
ただし、節句直前に慌てて飾ると、十分に楽しむ時間が取れないため注意しましょう。
一方で、あまり早く出しすぎるのも避けたいところ。
寒さが残る2月などに出すと湿気や温度差で人形や金具にダメージを与えることがあります。
保管環境が整っていない場合は、春分を過ぎて気候が安定してから出すのが安心です。
また、飾る期間の目安は約1か月。片付けは5月中旬までに行い、梅雨前に収納しておくと長く美しく保てます。
雨の日や湿度の高い日は避け、晴れた午前中に片付けるのが理想です。
縁起の良い日・六曜と飾る時間帯
鎧兜を飾る日を「六曜(大安・友引など)」に合わせる家庭もあります。
特に大安の日の午前中は「何事を始めるにも吉」とされ、飾りつけに最適といわれています。
「友引」は“幸福を分かち合う”意味があり、家族で準備を楽しむのにぴったりの日です。
ただし、「仏滅」や「赤口」は避ける人もいますが、現代では家族の予定を優先するケースがほとんどです。
六曜はあくまで気持ちの区切りとして捉え、無理に日取りを合わせる必要はありません。
飾る時間帯の目安
昔から「日が昇る明るい時間」に飾ると良いといわれてきました。
太陽の光には邪気を払い、家を清める力があると信じられてきたためです。
午前中〜昼過ぎに飾る家庭が多いですが、共働きなどで夜しか時間が取れない場合でも夜に飾って問題ありません。
明るい照明のもとで丁寧に飾れば、十分に縁起を保てます。
また、屋内で行うため天気の影響は少なく、雨の日でも大丈夫です。
重要なのは「家族で協力し、思いを込めて飾ること」。その行為自体に意味があります。
地域や家庭による違い
鎧兜を飾る時期やスタイルには地域差があります。
関東では春の彼岸明けから4月初旬にかけて出す家庭が多く、
東北や北海道など寒冷地では雪解けを待って4月中旬以降に飾るのが一般的です。
西日本では雛人形を片付けたあとに鎧兜を出す家庭が多く、
「桃の節句から端午の節句へ季節をつなぐ」風習が今も残っています。
住宅事情によって飾り方も変わります。
一軒家では床の間や和室に飾ることが多い一方、
マンションではリビングや玄関にコンパクトサイズの兜飾りを置くスタイルが主流です。
木製台座やアクリルケース入りなど、洋室にも合うモダンなデザインが人気で、
近年は「和モダンインテリア」として季節を楽しむ家庭も増えています。
祖父母から贈られる場合は、節句の2〜3週間前を目安に届くよう準備してもらうのが理想です。
家族全員が関わって整えることで、より思い出深い行事になります。
鎧兜を片付ける時期と注意点
端午の節句が終わったら、5月中旬〜下旬の晴れた日に片付けるのがおすすめです。
湿気の多い梅雨前に収納することで、カビや色あせを防げます。
片付けの際は次のポイントを意識しましょう。
-
風通しの良い場所で半日ほど陰干しする
-
手袋を着用し、金属部分に指紋を残さない
-
桐箱や防湿剤を活用して収納する
-
高温多湿や直射日光を避けた場所で保管する
-
翌年飾る前に点検・陰干しを行う
金具や布地は湿気に弱く、放置するとサビやカビの原因になります。
正しい手入れを続けることで、鎧兜を長く美しく保つことができます。
鎧兜を飾る意味と由来
鎧兜は、もともと戦で身を守るための装備でした。
その「身を守る」という意味が転じて、子どもを災いから守るお守りとして飾られるようになったのが始まりです。
端午の節句の起源は古代中国の「端午節」。
奈良時代に日本へ伝わり、菖蒲や蓬で邪気を払う風習が定着しました。
鎌倉時代には武家文化の影響で、勇ましい武具を飾って男児の成長を祝う風習へと発展します。
「菖蒲(しょうぶ)」が「尚武(武を尊ぶ)」に通じることもあり、
端午の節句は“強さ”や“健やかさ”の象徴として受け継がれてきました。
鎧兜の素材には、金箔・漆・正絹・真鍮などが使われ、職人の手によって一つひとつ丁寧に仕上げられています。
これらの伝統工芸技術は日本文化の象徴であり、現代の鎧兜は「飾る芸術品」としての価値も高まっています。
時代とともにデザインは変化しても、「子どもを守る」という願いは今も変わりません。
まとめ|昼が基本。でも大切なのは「心を込めて飾ること」
鎧兜を飾る時期は春分から4月上旬が理想で、昼間に飾るのが縁起良しとされています。
ただし、家庭の事情で夜や雨の日に飾ってもまったく問題はありません。
六曜や日取りよりも、家族の気持ちを込めて飾ることが最も大切です。
鎧兜を飾り、菖蒲湯に入り、柏餅を食べながら過ごす端午の節句。
近年はSNSで飾りつけを共有したり、記念写真を撮ったりと楽しみ方も多様です。
古くから続くこの伝統行事を通じて、家族の絆を深め、季節の節目を感じながら過ごしてみましょう。