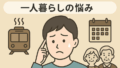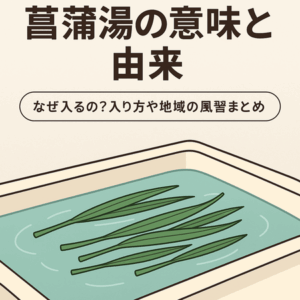
菖蒲湯とは?いつ入るもの?
菖蒲湯(しょうぶゆ)とは、端午の節句(5月5日)に菖蒲の葉や根をお風呂に浮かべて入る日本の伝統的な風習です。
古くから「菖蒲=尚武(武を重んじる)」に通じ、邪気を払うとされてきました。季節の節目に行われる行事のひとつで、今も地域によって受け継がれています。
菖蒲湯の由来と意味
菖蒲湯にはいくつかの由来があります。
-
邪気払いの意味
菖蒲の強い香りが邪気を祓うと信じられてきました。香りが強い植物を節目に使うのは、世界各地に見られる共通の風習です。 -
武家社会との関わり
「菖蒲」が「尚武(しょうぶ)」に通じることから、武士の間で縁起を担ぐ風習として広まりました。 -
端午の節句との結びつき
中国から伝わった「端午節」の習慣が日本に入り、季節の変わり目に健康と無病息災を願う行事として定着しました。
菖蒲湯の入り方
菖蒲湯は特別な作法があるわけではなく、一般的なお風呂に菖蒲を加えるだけで楽しめます。
-
菖蒲をよく洗う
-
葉をそのまま数本浴槽に入れる、または束ねて浮かべる
-
根を入れるとより香りが強まる(地域によって異なる)
お風呂の雰囲気が一気に季節行事らしくなり、リラックス効果も味わえます。
地域による違い
菖蒲湯の楽しみ方は地域によってさまざまです。
-
関東地方
葉を長く切らずにそのまま浴槽に入れることが多い。 -
関西地方
根の部分を使い、香りを強調する風習も見られます。 -
その他の地域
菖蒲を束ねて枕の下に敷く「菖蒲枕」や、菖蒲を軒に吊るす風習が残っているところもあります。
なぜ菖蒲湯に入るのか?
端午の節句は季節の変わり目で、昔は体調を崩しやすい時期でした。
そこで菖蒲の香りで邪気を払い、心身を清める意味を込めて菖蒲湯に入る習慣が生まれたとされています。
菖蒲湯と現代の楽しみ方
現在では「健康効果が科学的に証明されている」わけではありませんが、香りによるリラックスや行事を楽しむ文化的な意味合いで親しまれています。
スーパーや花屋で端午の節句が近づくと菖蒲が並ぶので、家庭で簡単に取り入れられます。
まとめ
菖蒲湯は、端午の節句に行われてきた伝統行事で、
-
邪気払い・無病息災を願う風習
-
地域ごとの特色ある入り方
-
香りを楽しむ文化的な習慣
として今も受け継がれています。
子どもから大人まで、家族で日本の季節行事を感じながら楽しめるのが菖蒲湯の魅力です。