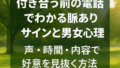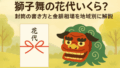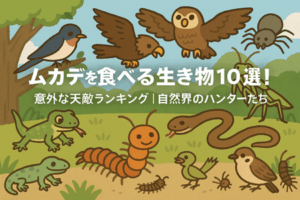
ムカデは鋭い顎と毒を持つ危険な存在として知られていますが、実は自然界では“食べられる側”でもあります。
山や森、さらには人の暮らす家の中でも、ムカデを捕食する天敵たちは数多く存在します。
この記事では、ムカデを食べる生き物10選 をランキング形式で紹介。
「ムカデが苦手」「自然に退治してほしい」という方にも、意外な味方が見つかるかもしれません。
🐍ムカデの天敵とは?自然界での立ち位置
ムカデは小型の昆虫やクモを捕らえて食べる“捕食者”ですが、同時に多くの動物にとっては“餌”でもあります。
食物連鎖の中で「捕食する側」「される側」の両方を担うことで、生態系のバランスを保っています。
ムカデが増えすぎると他の昆虫が減少し、逆にムカデが減りすぎると害虫が増える——。
その調整を支えているのが、今回紹介する天敵たちです。
🦎ムカデを食べる生き物①〜④【爬虫類編】
ヤモリ – 家の中でも見られる“ムカデハンター”
夜行性で壁や天井を自由に動き回るヤモリは、小型ムカデを素早く捕食します。
家の中で見かけると驚きますが、実はゴキブリやムカデを退治してくれる「天然の害虫駆除屋」。
家を守ってくれる存在として、むやみに追い出さない方が良い場合もあります。
トカゲ – 地上で活躍する俊敏な狩人
砂地や草原を俊敏に走り回るトカゲもムカデの天敵です。
強靭な顎で噛みつき、動きを封じてから食べます。
地域によっては小型のトカゲが庭などに生息しており、見えないところでムカデを減らしていることもあります。
ヘビ – 毒に強く、巻き付いて丸呑み
一部のヘビはムカデを主食にしています。
待ち伏せしてムカデに巻き付き、動きを止めてから丸呑みにする戦法。
特にシマヘビなどはムカデへの耐性が高く、自然界でムカデの数を調整する役割を担っています。
オオトカゲ – 頂点捕食者の力
モニターリザード(オオトカゲ)類は、ムカデの毒に強く、力強い顎で噛み砕きます。
ムカデだけでなく、他の昆虫や小動物も捕食し、食物連鎖の上位に位置する存在です。
🐦ムカデを食べる生き物⑤〜⑥【鳥類編】
ツバメ・スズメ – 雛のための栄養源
地上を移動する小型ムカデは、ツバメやスズメの餌になることがあります。
特に子育て時期のツバメは、豊富なたんぱく源としてムカデを巣に運ぶことも。
人間にとっては嫌な存在のムカデも、鳥たちにとっては大切な“命の糧”なのです。
フクロウ・タカ – 夜の空から狙う猛禽類
夜行性のフクロウや、鋭い視力を持つタカもムカデを捕食します。
強靭な爪とくちばしで動きを封じ、毒にもひるまず仕留める姿はまさに空のハンター。
夜の森では、ムカデが彼らの栄養源として生態系に組み込まれています。
🕷ムカデを食べる生き物⑦〜⑧【クモ・節足動物編】
アシダカグモ – 都市部最強のムカデキラー
日本の家屋にも出没するアシダカグモは、ムカデ・ゴキブリの両方を捕食します。
見た目は怖いですが、人間に害はなく「家の守り神」とも呼ばれる存在。
暗がりでムカデを見つけると、一瞬で噛みつき毒で動きを止めます。
ゲジゲジ – 素早い脚でムカデを翻弄
長い脚を使って素早く動くゲジゲジも、小型ムカデの天敵です。
攻撃を受ける前に素早く捕らえ、獲物を噛み砕きます。
見た目の不気味さとは裏腹に、ムカデ・ゴキブリ・シロアリなどを食べる「超有能な益虫」です。
🐜ムカデを食べる生き物⑨〜⑩【昆虫編】
オニヤンマ – 空から急襲する飛行ハンター
日本最大級のトンボ、オニヤンマは驚くほどの飛行能力を持ち、地表を動くムカデを狙って急降下。
鋭い顎で噛みつき、空中で捕食することもあります。
その俊敏さと攻撃力はまさに“空の狩人”。
大型カマキリ – 機会があればムカデも餌に
カマキリは基本的に昆虫食ですが、小型ムカデを見つけると捕食することも。
前脚でがっちりと挟み、反撃される前に食べてしまう。
昆虫同士の食物連鎖の一環として、自然界でのバランスを保っています。
🏡ムカデを減らすためにできる自然な対策
ムカデの天敵が多く生息する環境を保つことは、結果的にムカデの繁殖を抑えることにつながります。
庭やベランダでは殺虫剤を多用せず、自然に生き物が棲みやすい環境を整えるのがおすすめ。
たとえば、ヤモリやゲジゲジが住み着けるように壁面や隙間を完全に塞がない、
落ち葉を少し残して虫たちの生息スペースを確保するなど、小さな工夫が自然の防衛力を高めるポイントです。
また、夜に灯りをつけすぎると虫が集まり、結果的にムカデも誘引されるため、
屋外照明の使い方を見直すだけでも予防効果があります。
自然と共存しながらムカデを減らす——。
これこそが、人にも生態系にも優しい“持続可能な対策”といえるでしょう。
🌏まとめ|ムカデの天敵が生態系のバランスを支えている
ムカデは恐れられる存在ですが、自然界ではさまざまな生き物の命を支える“中間捕食者”。
爬虫類・鳥・クモ・昆虫など多様な天敵が存在することで、生態系のバランスが保たれています。
「ムカデ=悪者」ではなく、「自然の一員」として見てみると、身近な生態系の奥深さが感じられるはずです。