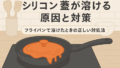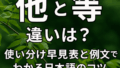はじめに:白がなくても肌色は作れる?
水彩画で人物を描くとき、「白を使わずに肌色って作れるの?」と悩む方は多いですよね。
実は、赤・黄・青の3色をうまく組み合わせれば、白なしでも自然で温かみのある肌色を作ることができます。
この記事では、水彩初心者でもわかりやすいように、
私自身の試行錯誤を交えながら「白なし肌色の混ぜ方」と「失敗しないコツ」を紹介します。
水彩で作る肌色の基本:3色だけでOK!
肌色の基本は、次の3色を混ぜて作ります👇
| 使用する色 | 役割 | 代表的な絵具例 |
|---|---|---|
| 赤 | 血色・あたたかさ | カドミウムレッド、ローズマダー |
| 黄 | 明るさ・自然さ | イエローオーカー、レモンイエロー |
| 青 | 落ち着き・影の色 | ウルトラマリン、コバルトブルー |
🔹 基本の配合比率
👉 赤:黄:青=1:3:0.5
黄色をやや多めに入れることで、白を使わなくても明るく自然なトーンになります。
混ぜたときに少し濃く感じても、水を多めに含ませればやさしい肌色に調整可能です。
白なしで肌色を作る手順(初心者向け)
STEP1:赤と黄を混ぜてベース色を作る
まずは赤と黄色を混ぜ、オレンジ寄りの明るい色を作ります。
この段階では“やや明るめかな?”くらいでOKです。
水彩は乾くと少し色が沈むので、塗る前より暗く見えることを意識しておきましょう。
STEP2:青をほんの少し足す
青を加えると一気に肌らしい落ち着いた色味になります。
ただし入れすぎるとグレーっぽく濁るため、筆先に軽くつける程度で十分です。
STEP3:水でトーンを整える
白を入れない分、水の量が明るさを左右します。
やわらかい印象にしたい場合は、筆をよく洗って水分を多めに含ませると◎。
紙の白が“光”の役割を果たし、自然な透明感が出ます。
失敗しないための3つのコツ
① 色を混ぜすぎない
最初から理想の色を作ろうとしすぎると、濁ってしまいます。
**「少しずつ足して確認」**を繰り返す方がきれいな発色になります。
② レイヤーを重ねて調整
肌の奥行きは、一度に作るよりも“薄く重ね塗り”で表現するのがポイント。
1層目:明るめの黄系
2層目:赤みを加えた色
3層目:影を意識して青・茶系
このように重ねると、自然な立体感が出ます。
③ 紙の白を“明るさ”として活かす
白絵具の代わりに紙の白さを残すことで、光を感じる仕上がりになります。
特に頬や鼻筋など、光が当たる部分を塗り残すと効果的です。
肌色のバリエーションを作るには?
| 目的 | 調整方法 | 例の配合 |
|---|---|---|
| 明るい肌 | 黄色を多め、水を多めに | 赤1:黄4:青0.3 |
| 健康的な肌 | 赤を少し強めに | 赤1.5:黄3:青0.5 |
| 日焼け肌 | 青・茶系を少量加える | 赤1:黄2:青1+バーントシエナ少々 |
日焼け肌や温かみのある肌を出すには、**オレンジ系(カドミウムオレンジ)**を足すと自然です。
透明感を出したいときは、ローズマダーをほんの少し混ぜるとピンクの血色が出ます。
紙と筆で変わる肌色の仕上がり
水彩は、使う紙や筆の種類によって肌の質感が大きく変わります。
たとえば「中目の紙」は滲みが柔らかく、初心者でもなめらかな肌を表現しやすいです。
一方で「細目の紙」は発色がよく、明るい肌を描きたいときに向いています。
筆は「丸筆(ラウンド)」がおすすめ。筆先を軽く動かすだけで、
頬や首筋の曲線を自然に表現できます。
慣れてきたら平筆でハイライト部分を塗り残すと、光の立体感が出せます。
透明感を出すための水の扱い方
肌の透明感は“水のコントロール”で決まります。
水を多めに含ませて塗ると、光が透けるような柔らかい色合いになります。
逆に水が少ないとマットになり、重たい印象に。
💡 コツ:
最初の1層目は水多め、2層目以降は少しずつ水を減らしていく。
乾くたびに色を重ねると、自然なツヤ感が生まれます。
光と影のつけ方でリアルさアップ
顔の中心(鼻・頬・額)は光が当たる部分。
影を付けるときは、ウルトラマリン+バーントアンバーをほんの少し混ぜて、
肌色の延長線上にある“やわらかい影”を描くとリアルです。
影を濃くしたいときも黒は使わず、
赤や青を少しずつ足して“肌色の深み”で陰影を作りましょう。
光源を意識すると、人物が一気に生き生きして見えます。
肌色づくりにおすすめの絵具ブランドと選び方
水彩絵の具はメーカーによって発色が少しずつ違います。
初心者の方なら、扱いやすく混色しやすいブランドを選ぶのがおすすめです。
-
ホルベイン(Holbein):発色が明るく、水に溶けやすい。練習向き。
-
ウィンザー&ニュートン(W&N):透明感があり、重ね塗りがきれいに出る。
-
ターナー(Turner):価格が手頃で初心者にも人気。
肌色を作るときは、同系統のメーカーでそろえると色の調整がしやすく、
思った通りのトーンが再現しやすいです。
まずは6〜12色セットで十分練習できます。
混色パレットの使い方とメンテナンス
絵具を混ぜるパレットも、実は肌色づくりの仕上がりを左右します。
白いプラスチックパレットは色の確認がしやすく、
洗いやすいので初心者には最適です。
混色スペースを使い分け、赤・黄・青をそれぞれ別エリアで管理すると
濁りが減り、クリアな肌色を保ちやすくなります。
使い終わったらすぐに洗い流しておくことで、
次の練習のときに色残りで失敗するリスクも防げます。
肌色づくりを楽しむ練習アイデア
-
色見本カードを作る
→ 混ぜた色ごとに比率と名前を記録しておく。 -
同じ比率で水の量を変える
→ 明るさと透明感の違いを体感できる。 -
写真を見ながら再現練習
→ 実際の肌トーンを観察して再現する力がつく。
これを繰り返すうちに、感覚的に「赤をもう少し足そう」「青を控えよう」が
自然にわかるようになります。
まとめ:肌色づくりは“水と光”のバランスがカギ
白を使わなくても、赤・黄・青の3色で自然な肌色は十分作れます。
ポイントは「少しずつ混ぜる」「紙の白を残す」「水で明るさを調整」。
初心者こそ、完璧を目指さず“何度も試して肌色を育てる”気持ちでOK。
あなたの筆から生まれる、世界に一つだけの肌色を楽しんでください🎨✨